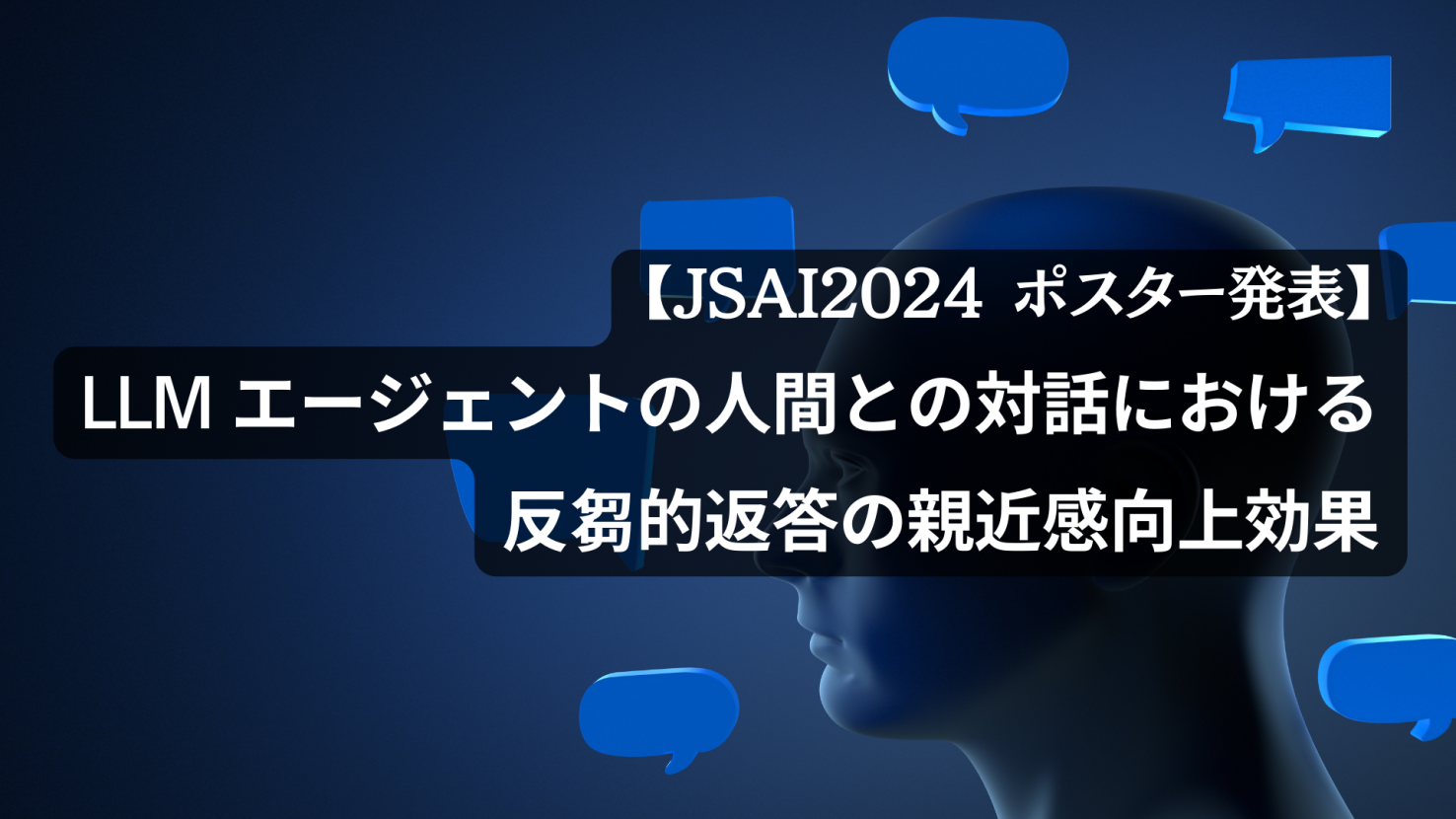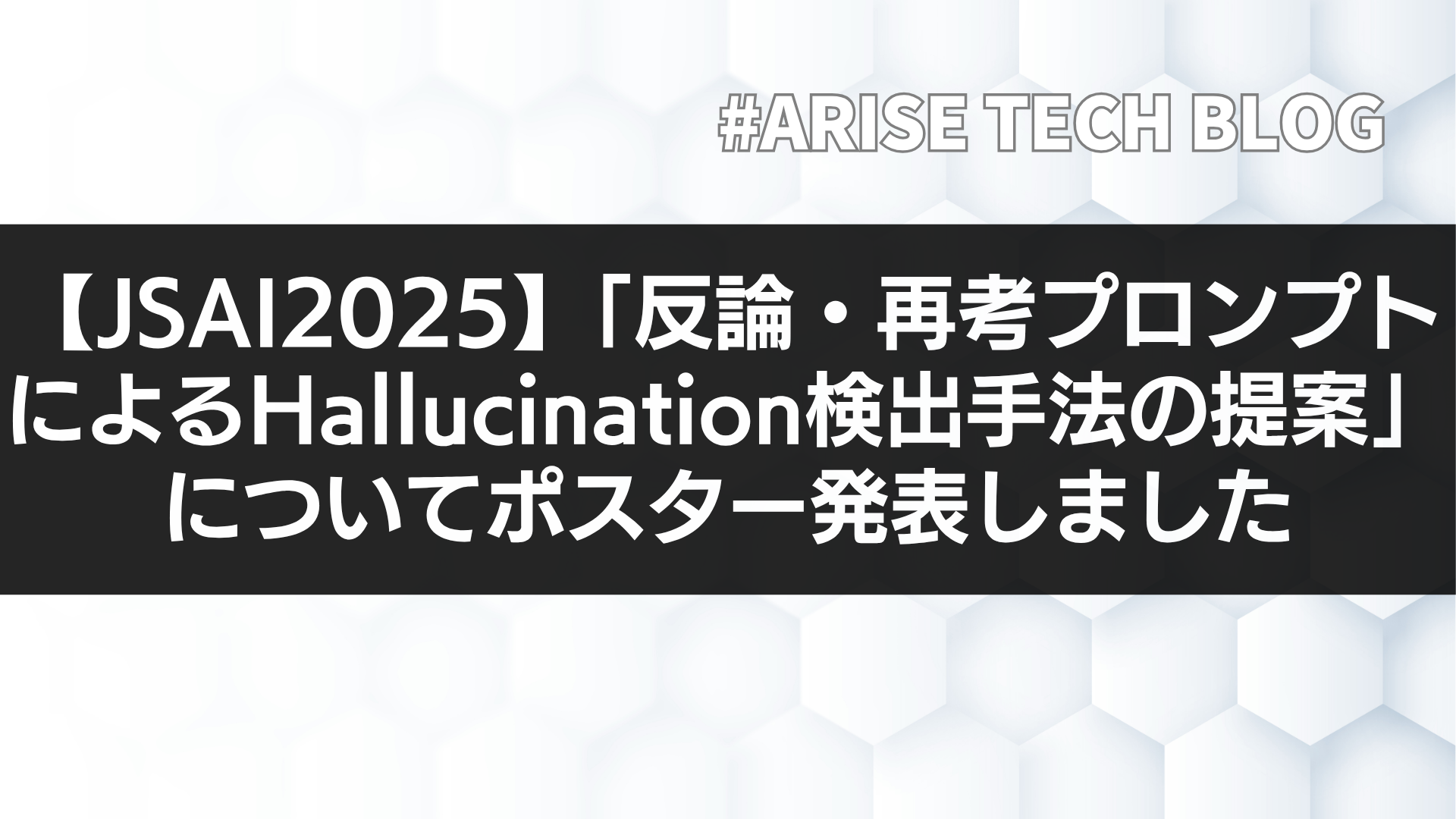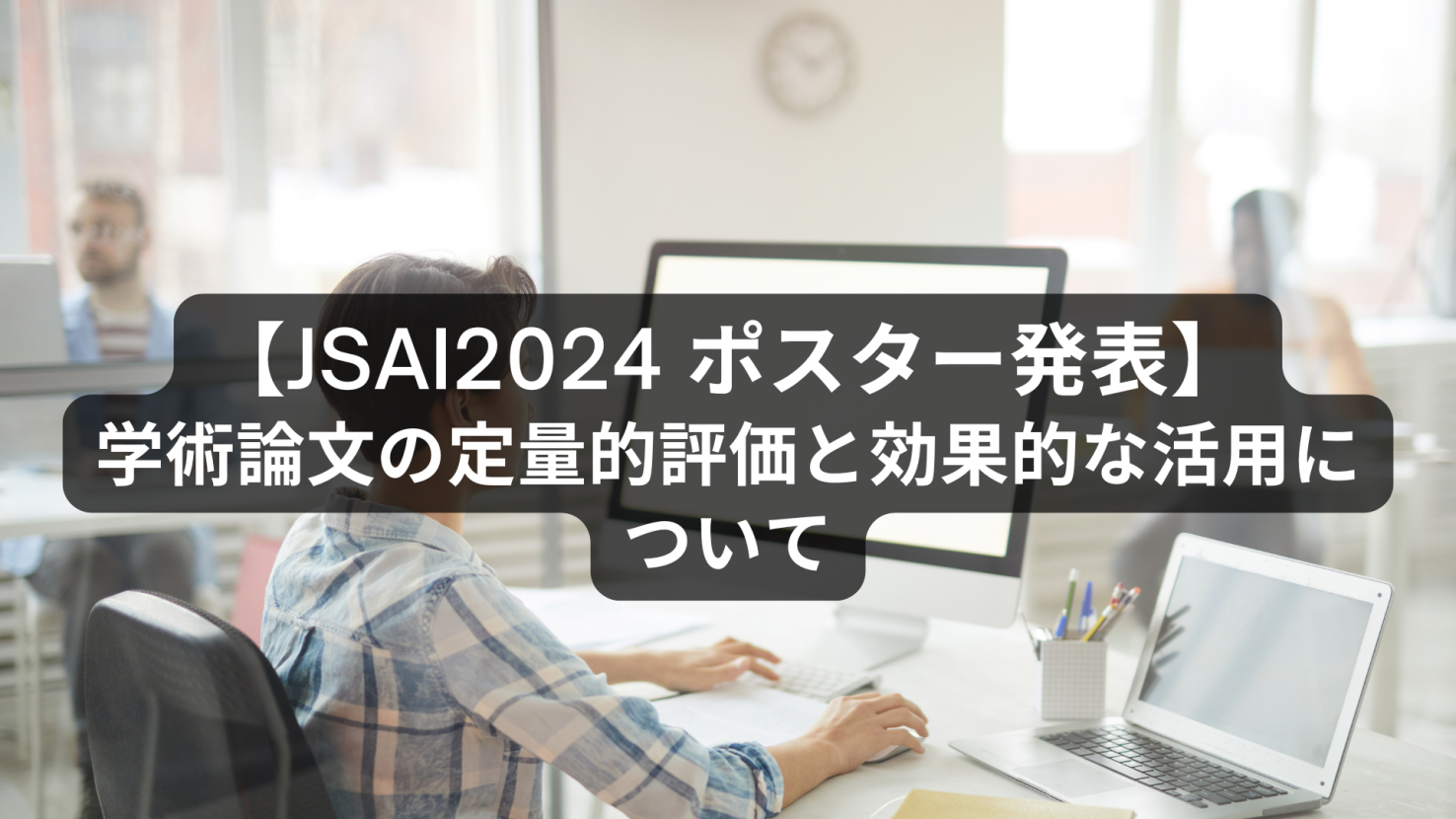TECH BLOG
JSAI2025参加レポート:対話AIとPhysical AIの最前線を追う
目次
はじめに
こんにちは、AIエンジニアの芹澤です。
この記事は、2025年5月27日 (火) 〜 2025年5月30日 (金) に開催された第39回 人工知能学会全国大会 (JSAI2025) の参加レポートとなります。私自身の関心に基づき、特に印象的だった発表をピックアップしてご紹介します。
今年のJSAIは万博も開催されている大阪にあるグランキューブ大阪で開催され、過去最多となる4,922名が参加、1,178件の発表があったそうです。生成AIを中心とした盛り上がりを背景に、AI分野への関心の高さを肌で感じる大会となりました。
 https://x.com/kiyota_yoji/status/1928570153291092243 より
https://x.com/kiyota_yoji/status/1928570153291092243 より
ARISE analyticsでも、ランチョンセミナーやインダストリアルセッションでの登壇のほか、企業展示ブースの出展やポスター発表など、各所でJSAIに参加させていただきました。これらの詳細についてはまた別記事を公開予定ですので、そちらもぜひご覧ください。
※参考(ARISE analytics 公式note):2025年度 人工知能学会 全国大会に参加しました
注目した発表① Human Agent Interaction (HAI) 領域
まず前提として、私は人とAIのコミュニケーションという分野 (Human Agent Interaction; HAI) に興味を持っており、以前から技術発信や学会発表を行っています。詳細については、以下の記事を参考にしていただけると嬉しいです。
今回のJSAIでも、この分野の発表がいくつか見られましたので、特に注目した発表について僭越ながら紹介と個人の感想を書かせていただこうと思います。
AIの説明表現が意思決定に及ぼす影響
著者・所属:大社 綾乃1、楊 明哲2、馬場 雪乃2 (1. 株式会社豊田中央研究所、2. 東京大学)
プログラムリンク:JSAI2025/The Impact of AI Explanation Tone on Decision-Making
人はAIシステムを信頼していても、AIの提案に従うとは限らないことから、AIの説明表現のトーンが意思決定に及ぼす影響をAIの役割とユーザ属性の観点から明らかにするという発表でした。「信頼 = 従うとは限らない」という仮定が興味深く、人間同士の関係にも通じる部分があることから、どう比較するのかについて注目しました。実験結果としても、AIの役割とユーザ属性によって影響が異なるという傾向が見られ、興味深く聴講しました。会場の聴講者も多く、関心の高さを感じる発表でした。
対話型 LLM を用いた capitalization による情緒的支援の原理的検証
著者・所属:泉谷 一磨1、窪田 進一1、地頭江 悠太2、安達 滉一郎2、新潟 一宇1、滝沢 龍2 (1. 株式会社リコー、2. 東京大学)
人間のストレス管理のツールとして、LLMを用いた対話システムにcapitalizationという心理効果を活用し、情緒的支援を行うという発表でした。私が昨年行った研究でも心理効果を適用したLLMモデルによる検証ということを行っていたため、研究の近さを感じ聴講しました。AIが情緒支援を行うというとあまり向いていない使い方のように感じたため、どの程度有効なのか注目しました。結果として、感情支援に活用可能という結論になっており、今後の大規模検証などを期待したいなと思いました。
注目した発表②Physical AI領域
最近は、個人的な興味領域としてPhysical AI、すなわち物理世界で動作するAI(ロボット)注目しています。
Physical AIは、従来の画面上でのAIとは異なり、物理世界での行動を伴うAI技術であり、ロボティクス、自動運転、製造業など幅広い分野での応用が期待されています。この領域は先日NVIDIAからヒューマノイド向け基盤モデル GROOT N1が公開されたり、AIロボット協会 (AIRoA) が立ち上がり、国産ロボット基盤モデルの構築が進められているなど、今後注目される領域の一つかと思います。
今回のJSAIでもロボット関連のセッションが複数あり、中でも注目していたセッションについてご紹介します。
企画セッション:フィジカルAIシステムの研究開発 ~身体性に基づく知能の研究~
プログラムリンク:JSAI2025/フィジカルAIシステムの研究開発 ~身体性に基づく知能の研究~
このセッションはオーガナイザーの茂木先生を中心に、尾形先生をはじめとしたAI・ロボット分野のトップを走る先生方がパネルディスカッション形式でPhysical AIについて語り合うものでした。
パネルディスカッションでは複数のお題が用意されていましたが、中でも「ロボットはデータでChatGPTモーメントを起こせるか」というテーマは個人的に興味深く感じました。ChatGPTが大規模言語モデルによって自然言語処理分野に革命をもたらしたように、ロボット分野でも同様のブレイクスルーが起こりうるかという問いです。登壇者の多くは「現在の延長線上では難しい」としながらも、ロコモーション技術の進歩や、今後オンラインデータを活用した学習への期待など、希望も語られていました。
また、「日本の勝ち筋はどこにあるか」というテーマの中で、日本は実機重視なので、もっと積極的にシミュレーションも活用して生かしていくべきというお話が出ました。日本のロボット研究は伝統的に実機での検証を重視してきましたが、近年のシミュレーション技術の向上により、より効率的な研究開発が可能になってきています。私自身も今後シミュレーションでAIロボットについて検証を進めようと思っていたため、そのような背景と提案があるのは嬉しく思い、共感しました。
おわりに
JSAIは年に一度のAIのお祭りのような場ですが、改めてAI領域に関わる人たちの熱と勢いに触れることができ、自身の取り組みのモチベーションをアップさせることができました。人工知能学会というとAIだけのように思われがちですが、今回紹介したようにAIロボット領域の発表など近隣領域を巻き込んで非常にバラエティー豊かな発表が聴けるのがこの学会の特徴かなと思います。この記事を通じて、少しでもJSAIや最新のAI研究に興味を持っていただけたら嬉しいです。来年のJSAIで皆さんとお会い出来るのを楽しみにしています!
また、6/18 (水) に弊社主催でJSAI2025の振り返りLT会も開催予定です。複数のデータサイエンティストがそれぞれの目線でよかった論文について紹介しますので、以下のリンクよりぜひご参加ください。
JSAI参加報告会~生成AIに注目して~【 ABEJA × ARISE analytics 】 - connpass
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 この記事をシェアする
この記事をシェアする